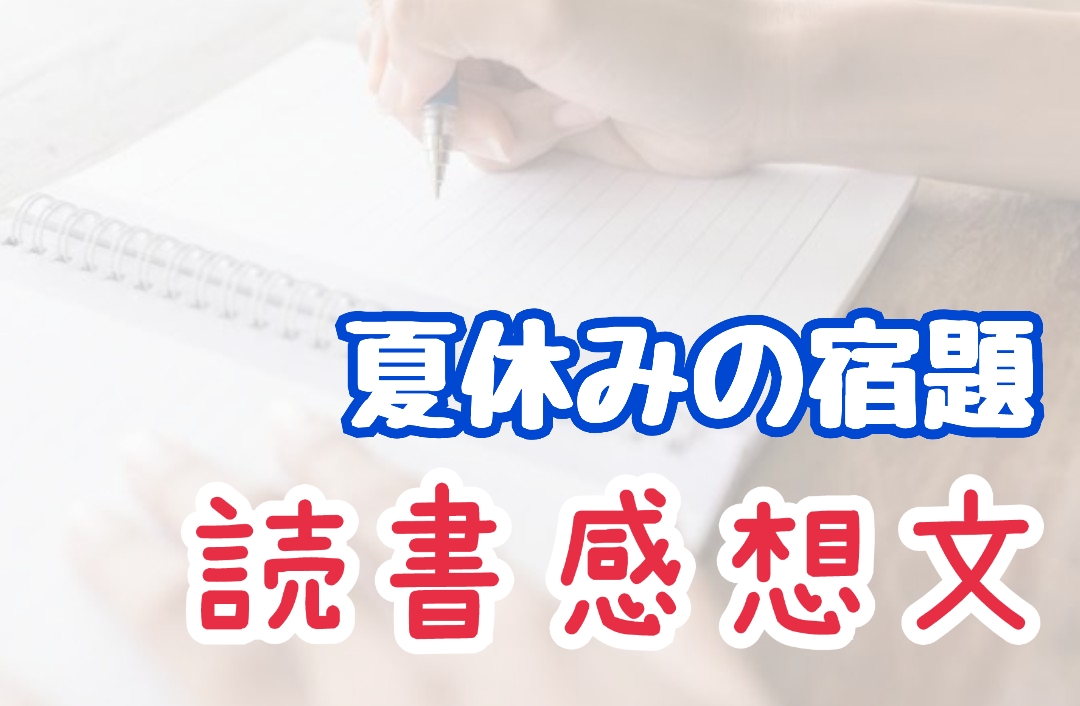
【小学1年生向け】親子でバトルしながら夏休みの宿題・読書感想文を書き始めるコツ
夏休みの宿題で多くの保護者が悩むのが、「読書感想文」です。我が子は、小学校の授業でも学んでいないこともあり、読書感想文の書き始めの段階で壁にぶつかりました。入学間もない小学1年生は、文章を書くこと自体がまだ慣れていないため、最初の一文でつまずくことがよくあるそうです。この記事では、我が家での読書感想文親子バトル、そこから学んだ1年生でもスムーズに書き始められる方法や例文をご紹介します。
Contents
初めての読書感想文
小学校に入学して早数カ月となり、夏休みに入りました。我が家では、読書感想文や絵日記の宿題が出ましたので、時間のかかることは早めにやってしまおうという作戦に出ました。
夏休みの宿題サポート
毎日の宿題で、勉強する習慣がついてるかと思いきや、意外と自分から宿題をやろうとする姿勢が全くありませんでした。1年生なので仕方ないと分かってはいましたが、せっかく学んだことを夏休みの間で忘れてしまっては可哀想です。
なので、少しずつでも良いので漢字や算数のプリントを与えて行くことにしました。日々の積み重ねが力になるということも学べそうなので。
それと並行して、読書感想文もできたら良いと考えていました。
読書感想文は本当に大変
まず感想文に慣れていない子供が、本を読んで作文を書こうとすると、本の内容をそのまま書くことがあります。これはこれでもしかしたら良いのかもしれませんが、せっかく学ぶ機会なので、原稿用紙の使い方から教えてあげることにしました。
大人なら当たり前に知っている、書き始めの最初は1マスあけることもわからないので、かなり根気が必要になります。
我が家は書き始めの書き方が定まらず、どうやって始めたらいいのか、親子共々イライラとすることもありました。
「書き始め」が一番大切で一番難しい
文章の出だしは、感想文全体の流れを作る大事な部分。書き始めが固くなると、その後の文章もぎこちなくなりがちですよね。反対に、書き出しが自然だとスラスラと書き進められるようになります。私自身は、小学校のときに読書感想文が大の苦手でした。今現在、うまく書けない子どもの姿を見て、ものすごく気持ちがわかります。
そこで我が家では、書き出しの例文を作るために、インタビュー形式で子どもから色々と聞き出しました。
一応、親の中での書き始めの形を目標にして、この本は何で選んだの?自分が思ったとおりに教えて?と聞いていきました。
小学1年生でも出来た!書き始めの作り方
- 読んだきっかけから始める
例:「この本には、好きな動物が出てくるから選びました。」 - 一番心に残った場面から始める
例:「うさぎが道にまよったところが、とてもおもしろかったです。」 - 登場人物や動物の紹介から始める
例:「この本には、やさしいくまさんがでてきます。」
この様な感じで、インタビューをしながら例文の大まかな材料を集めていきました。
1年生でも使いやすい書き始め例文
- 「わたしは〇〇という本をよみました。」
- 「よんでいて、〇〇のところがすきになりました。」
- 「このおはなしは、〇〇がでてくるたのしいおはなしです。」
- 「〇〇をよんで、わたしは〇〇だとおもいました。」
スムーズに書き始めるための親のサポート
低学年の子どもにとって、最初の一文は親が一緒に考えてあげるのが効果的です。苦手な子は3年生でも手伝うこともあります。本の内容も難しくなってくるので、その子に合ったサポートができると良いですね。
質問をしながら会話形式で引き出すと、自分の言葉で書けるようになります。質問しても返ってこない場合もあり、ちゃんと答えて!とバトルが始まることもありましたが、次第に親子は冷静になりました。
- 「どんなところが一番おもしろかった?」
- 「だれが出てきた?」
- 「読んでからどんな気もちになった?」
感想文というと、1年生にとってみたらわからないこともあります。感想っていうのは、どういうふうに思った?とかどんな気持ちになった?っていう、自分が思ったことなんだと言うことも理解してると読書感想文が書きやすいですね。
完成したものが親としては納得いかないかもしれませんが、子供と一緒に作ったこと、作文のルールが学べたこと、夏休みに本を読み込んだこと、これらはしっかりと子供の糧になるのかなと思っています。
まとめ
小学1年生の読書感想文は、書き始めをシンプルにすることで最後まで書きやすくなることがわかりました。読んだきっかけ・印象的な場面・登場人物のどれかからかスタートするとスムーズに仕上げることが出来ます。
長い夏休みもあっという間に終わりますが、宿題の中でも一番時間のかかるものになります。脳みそフル稼働で子どもも大変だと思います。保護者の方は、質問で会話を広げながら、子どもが自分の言葉で書けるようにサポートしてあげると良いですね 。
投稿者プロフィール
- 役職:父親
- はじめまして!3児のパパ(仮)と申します。東京出身。高校時代に人の役に立ちたいと思い、医療福祉系の道へ。医療福祉系の資格を多数取得しています。子育てのこと、生活やお金のノウハウや為になったことを発信することを目的に当ブログを開設しました。メルカリでも色々と販売しています!


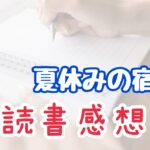

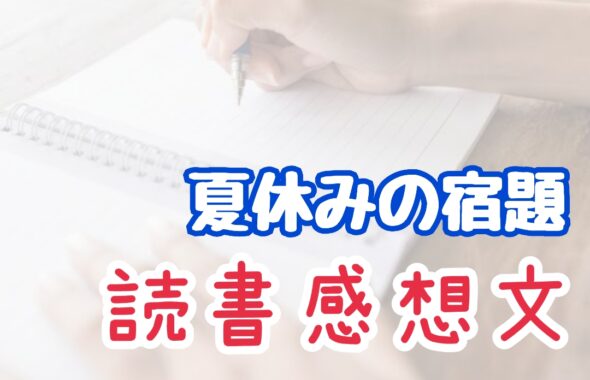




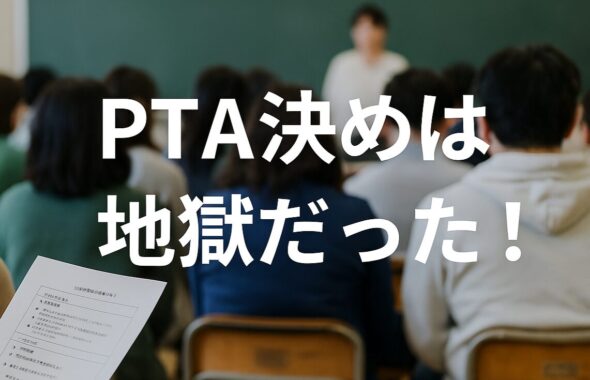
この記事へのコメントはありません。